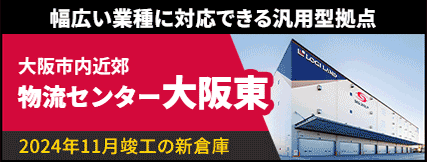【物流業向け】ピッキングとは?
意味・種類・効率化の工夫をわかりやすく解説
「ピッキングとは何か?」と疑問に思う方が増えています。ピッキングは倉庫全体の工数の半分近くを占めるとも言われ、正確さとスピードが顧客満足やコスト削減に直結する工程です。ここでは、ピッキングの基本的な意味から作業プロセス、種類や方式ごとの特徴、効率化の工夫や最新動向までをわかりやすく解説します。
ピッキングとは?意味と定義をわかりやすく解説
ネットで頼んだ商品が翌日に届くのは、倉庫で何が起きているからでしょうか?その舞台裏の中心にあるのが「ピッキング」です。ピッキングとは、倉庫で伝票や端末の指示どおりに必要な商品(在庫管理上の単位=SKU)を棚から正確に集め、注文ごとに数量や期限を確認して出荷のためにそろえる作業のことです。現場の担当者は、棚番号を頼りに歩き、バーコードを読み取りながらカゴ車に商品を入れていきます。あなたがコンビニで受け取る荷物も、誰かがこの工程を正しくこなした結果です。

ピッキングとは何か?物流現場での定義
現場では、担当者が「バラ(1個ずつ)」「ケース(箱単位)」のどちらで集めるかを決め、紙のリストやハンディ端末、時にはボイスピッキング(音声案内方式)で指示を受けます。また、単一注文を1件ずつ拾う「シングル」と、複数注文をまとめて拾う「バッチ(まとめ取り)」、エリアごとに分担する「ゾーン」などの方式があります。企業がこの違いを理解すると、扱う商品や注文の特性に合わせて最適な道具と動線を設計できます。つまり、定義を正しく押さえることにより、ムダな歩行や取り違えを減らし、教育もしやすい標準手順を作れるのです。
ピッキングが果たす役割
倉庫の流れは、入庫→保管→ピッキング→検品→梱包→出荷という順番で進みます。ピッキングはこの中で「正しい品を、正しい数、正しいタイミングで」次工程に渡すゲートの役割を果たします。現場がここで誤ると、検品や梱包で手直しが発生し、再配送やお詫び対応でコストが膨らみます。例えば誤出荷率が0.1%でも、1万件で10件のやり直しが生まれ、往復送料と再作業で1件あたり数百円〜千円超の負担になることがあります。企業がこの役割を重視すると、納期の安定と顧客満足の向上に直結します。
なぜピッキングが重要なのか
多くの倉庫では、作業時間の中で「歩く時間」が大きな割合を占めます。現場が棚配置やルートを工夫して歩行を20%削れれば、同じ人数でより多くの注文に応えられ、出荷の遅れを防げます。さらに、担当者がハンディでスキャンしながらダブルチェックを行うと、取り違えは大きく減ります。繁忙期の午前9時、端末に表示された波(まとまった注文の束)を見た担当者が、ショートカットの動線でテキパキ回る――この小さな積み重ねが、翌日配送の土台になります。では、ピッキングの改善が実際にどんな効果をもたらすのでしょうか。代表的なポイントは次の3つです。
- 精度の向上:スキャンや棚番の徹底により誤出荷を予防できます。
- 速度の向上:バッチやゾーンの使い分けで歩行を短縮できます。
- 安全と品質:高所・重量物の手順を明確にして事故と破損を防げます。
これらは単なる効率化ではなく、現場の安全・顧客満足・コスト削減を同時に実現する基盤となります。企業がピッキングの精度と効率を両立できれば、レビュー評価やリピート率が上がり、安定した成長につながります。次の章では、代表的なピッキング方式と、今日からできる効率化のコツを紹介します。
ピッキングの作業プロセス|倉庫で商品を取り出す一連の流れを解説
ピッキングって、結局どんな順番で進むの?と感じたことはありませんか。たとえばスマホで「今日中に欲しい」と注文した商品が翌日に届くのは、倉庫の中でピッキングが素早く正確に回っているからです。ここでは、現場で実際に何が起きているのかを、身近な例と一緒にたどっていきます。

-
発注から出荷までの流れ
お客さまがECサイトで注文すると、注文データは倉庫管理システム(WMS=倉庫の在庫や作業を管理する仕組み)へ届きます。システムはだれがどの順で取るかを決め、現場スタッフに指示を出します。スタッフは棚番号と通路順に沿って商品を集め(ピッキング)、検品担当がバーコードをスキャンして商品と数量を確認します。検品が終わると、梱包担当が緩衝材や伝票を入れて箱を閉じ、送り状を貼り、出荷ゲートへ運びます。こうした流れが整っていることは、納期を守るためだけでなく、誤出荷を防いで返品や再配達のムダを減らすために重要です。なぜなら、ひとつのミスが配送の遅れや在庫ズレに直結し、結果としてお客さま満足度と売上に影響するからです。
-
ピッキングリストの活用方法
現場では、紙のピッキングリストやハンディ端末(スキャナー付きの小型端末)を使って、棚の場所・商品名・数量・SKU(在庫管理上の1商品単位)を確認します。スタッフは「シングルオーダー(1件ずつ集める)」か「バッチ/マルチオーダー(複数件をまとめて集める)」を選び、通路のムダな歩行を減らします。リストの並び順を通路の順番に最適化し、バーコードで必ず照合する運用にすると、取り違えミスが大きく減ります。実際に、スキャン必須に切り替えた事例では誤出荷率が約3分の1になり、1件あたりの歩行距離も2〜4割短くなることが多いです。これは、目視確認だけに頼らない仕組みづくりが、熟練度に左右されない安定品質を生むからです。
活用のポイントは次のとおりです。
- 並び順を「最短ルート」に最適化する
- バーコード必須でスキャン照合を徹底する
- 代替ロケーションや商品写真を表示し迷いを減らす
これらを実行することにより、作業スピードと正確性が同時に上がり、繁忙期でも崩れにくい体制をつくれます。
-
在庫管理との関係性
ピッキングは、在庫管理と常にセットで動きます。スタッフが商品を取ってスキャンすると、システムはその瞬間に在庫を引き落とし、棚の残数とECの表示在庫を同期します。倉庫はロケーション管理(棚の住所を明確にすること)や先入れ先出し(FIFO=古い在庫から出すルール)を守り、サイクルカウント(毎日少しずつ数える簡易棚卸し)でズレを早期に見つけます。これを怠ると、システムの画面上は在庫があるのに実棚が足りない「売れてから欠品が判明する状況」が起き、出荷遅延やキャンセルにつながってしまうのです。正確な在庫とピッキングの即時反映は、欠品の防止だけでなく、過剰在庫の抑制や保管コストの削減にも効きます。つまり、ピッキング精度の向上は、そのまま在庫精度の向上であり、販売機会の最大化に直結するのです。
ここまでの流れが腹落ちすると、次に気になるのは「どのやり方を採用すれば、うちの倉庫はもっと速く正確になるのか」という点です。次の章では、ゾーンやバッチなどのピッキング方式の選び方と、現場が今日から変えられる改善策を紹介します。
ピッキングの種類|シングル・バッチ・ゾーンの違いと特徴
ピッキングのやり方で、出荷のスピードやミスの数がどれくらい変わるか、想像したことはありますか?たとえば夕方の注文ピークで、人があちこち歩き回っているのに荷物がなかなか出ない…そんな光景には、方法の選び方が大きく影響しています。ここでは代表的な3つの型を、現場のイメージと一緒にかみ砕いて紹介します。
シングルピッキング(オーダーピッキング)
担当者は1件の注文ごとに棚を回り、必要な商品だけを集めます。ネットショップで「Aさんの3点セットを取りに行き、終わったら次はBさん」という進め方です。チェック対象が1注文に絞られるため、担当者は伝票と実物を一対一で照合しやすく、誤出荷を抑えやすいことが事実です。ただし担当者は注文ごとに同じ棚を何度も往復しやすく、歩く距離が長くなりがちです。
この方法が重要なのは、立ち上げが速く教育が簡単だからです。新人の担当者は流れをすぐ理解でき、ギフトの個別指定やメッセージ同梱など“注文ごとに違う”要望にも柔軟に対応できます。そのため、SKU(在庫管理上の単位=商品)が多くて各SKUの注文数が少ない「多品種少量」の倉庫や、立ち上げ期の現場に向いています。
トータルピッキング(バッチピッキング)
担当者は複数の注文をまとめ、SKUごとに必要数量を一気に集めます。たとえば「今日のTシャツ白Mは合計30枚」と先に回収し、その後で仕分け台やソーター(仕分け機)で注文単位に分けます。担当者は同じ棚を一度で回収できるため、歩行距離を短くでき、集品速度を上げやすいことが特徴です。一方で、後工程の仕分けが必須になるため、仕分けミスを防ぐ表示や道具の設計が欠かせません。
これが重要なのは、注文に共通する商品が多いタイミング(セール品や定番商品の波)で圧倒的に効率が上がるからです。企業が夕方のピークに5件ではなく50件の注文をさばくとき、移動のムダを減らせるかが出荷数を左右します。バッチを組むことで、企業は人時(人×時間)当たりの出荷数を底上げし、運賃の締め時間にも間に合わせやすくなります。
ゾーンピッキング・ウェーブピッキング
ゾーンピッキングは、企業が倉庫をエリアに分け、担当者が自分のゾーンの品だけを集める方法です。トート(取っ手付きの箱)やカートがゾーンを順に回り、最後に結合ステーションで注文を完成させます。担当者は慣れた棚だけを相手にするため迷いが減り、通路の混雑も抑えられます。ただし結合の管理や進捗の可視化が要となり、バーコード照合などの仕組みを整える必要があります。
ウェーブピッキングは、企業が出荷締め時間や配送便に合わせて注文を時間帯や便ごとにまとめて一斉に処理する考え方です。たとえば、朝は大型店舗向けの注文をまとめて処理し、午後は宅配便向けの注文をまとめる、といった具合です。このように時間帯ごとの「まとまり(ウェーブ)」ごとにピッキング方法(シングル/バッチ/ゾーン)を組み替えられるのが特徴です。これは現場の負荷を平準化しつつ、トラックの積み込みやラベル発行の締めに確実に合わせられるからです。
これらピッキングの使い分けはまとめると以下の通りです。
- 小さな倉庫で商品数が多い場合は、1件ずつ注文を処理するシングルピッキングが向いています。
- 同じ商品をまとめて出荷することが多い時間帯は、一度にまとめて取り出して後から分ける「バッチピッキング」が効率的です。
- 倉庫が広かったり、通路が混雑しやすい場合は、エリアごとに担当を分ける「ゾーンピッキング」に加え、出荷時間を区切る「ウェーブピッキング」を組み合わせると効果的です。
結局のところ、どのピッキングも「誰がどれだけ歩き、どこで確認し、いつ出すか」を設計するための道具です。企業が注文が集中する時間帯や商品の偏りを見える化すると、最適解ははっきりしてきます。次の章では、現場の規模や品ぞろえに合わせたピッキングの具体的な選び方と組み合わせのコツを紹介します。
ピッキング方式と特徴|現場に合わせた効率的な選び方
セールの日、倉庫の通路を何度も行ったり来たり。「もっと速く、間違えずに取れないかな?」と感じたことはありませんか。ピッキングのやり方は一つではなく、現場の規模や商品特性に合った方式を選ぶことで、スピードも正確さも大きく変わります。

人が商品棚へ移動する方式(Man to Goods)
この方式では、作業者がカートを押し、ハンディターミナル(携帯型のバーコード読み取り機)を持って棚を回ります。近所のスーパーで買い物リストを片手に売り場を歩くイメージに近いです。小規模〜中規模の倉庫や、日々レイアウトを変えたい現場で広く使われています。初期費用が少なく、すぐに立ち上げできることが事実としての強みです。
さらに、この方式は柔軟性にも優れています。EC(ネット通販)の流行や季節要因で品ぞろえが頻繁に変わるときでも、棚の入れ替えだけで対応できるからです。その一方で、作業者が歩く距離が長くなりやすく、疲労や作業品質のばらつきにつながる点は避けられません。スピードや正確さが人に依存しやすいこともあり、効率を保つためにはゾーン分け(担当エリアを決める)やマルチオーダー(複数注文をまとめて取る)といった工夫が欠かせません。
つまり、この方式は「導入が簡単で柔軟に使える」という利点を持ちながらも、「人の歩行負担と品質の安定性」が課題になる方式といえます。現場の規模や商品特性に合わせ、シンプルさを活かしつつ改善策を組み合わせることが成功のポイントです。
商品が人の元に届く方式(Goods to Man)
この方式では、コンベヤやリフト、シャトル(自動で箱や棚を運ぶ台車)やAS/RS(自動倉庫)が商品を作業者のステーションに運びます。作業者はその場から動かず、届いた箱や棚の品をスキャンして仕分けます。たとえば、色違いやサイズ違いが多いアパレルECでは、次々と対象商品が目の前に届くので、取り違えを減らしやすいです。人が歩かないという事実が、疲労とムダ時間の削減に直結します。
歩行がほぼゼロになることで、1時間あたりの処理数が安定し、教育期間も短くできます。これは繁忙期に短期スタッフを多く投入する現場で特に重要です。ただし、初期投資やレイアウトの制約、システム連携(在庫データやバーコードの整備)が必要になります。大型や不定形の商品が多い場合は向き・置き方の設計が難しくなるため、対象SKU(在庫管理上の単位=商品)を絞って段階導入するのが現実的です。
ロボットや自動化システムによるピッキング
最近は、AMR(自律走行ロボット=倉庫内を自動で走る台車)が棚や箱を運んだり、ピースピッキングロボット(ロボットアーム)が1点ずつつかみ取ったりする事例が増えています。夜間はロボットが静かに搬送を進め、日中は人が仕上げる、といったハイブリッド運用も可能です。高速ソーター(自動仕分け機)を組み合わせれば、店舗別・地域別の仕分けもスピーディーにできます。自動化が「歩く・探す・数える」といった単純作業を代替することは事実であり、人は検品や例外対応など頭を使う工程に集中できます。
これは、人手不足と繁閑差が大きい今の物流にとって重要です。必要なときに台数を増やし、落ち着けば台数を戻すなど、ロボットは“伸び縮み”しやすいからです。一方で、導入費用、保守、そして例外処理(透明・柔らかい商品のつかみ取りなど)が課題になります。成功の近道は、バーコード整備や棚番の明確化、動線の標準化を先に行い、小さく試して(パイロット導入)効果と課題を見極めることです。
どの方式にも向き不向きがあります。次の章では、現場規模やSKU数、予算に合わせた選び方と導入ステップを具体的に解説します。
ピッキング効率化の工夫|動線改善・IT活用・人員配置のポイント
「今日の出荷、倉庫を何往復もして息が上がった…」そんな日、ありませんか?ピッキングは「歩く」・「探す」・「確かめる」の連続です。だからこそ、棚の並べ方や指示の出し方を少し変えるだけで、スピードもミス率も大きく変わります。

-
棚のレイアウト最適化
朝9時、同じ商品を何度も取りに戻る──現場ではよくある光景です。倉庫が「売れやすい商品を出荷口の近くに」「腰から胸の高さ(取りやすい高さ)に」「重いものは下段、軽いものは上段に」置くと、歩く距離と手を伸ばす回数がぐっと減ります。よく一緒に注文される組み合わせは隣同士に置き、通路は一方通行でぐるっと回れる動線にすると、迷いも渋滞も起きにくくなります。さらに、棚の並び順をピッキングリストの順番と合わせると「順路どおりに取るだけ」になり、新人でも迷いません。これが重要なのは、1件あたり数十秒の短縮でも、1日数百件で見ると何時間もの差になるからです。そのうえ探す時間が減ることで取り違いも減り、繁忙期の増員でも品質を落とさずに回せます。
-
デジタルピッキングシステム(DPS)の活用
DPSは、棚のランプが光って数量を表示し、作業者が光った場所から指定数を取り、ボタンで完了を知らせる仕組みです。紙のリストを目で追う必要がなくなり、システムが複数の注文をまとめて案内するので、「まとめて集めて、光で分ける」動きができます。現場がDPSを使うと、視線移動が減って手元に集中でき、取り間違いが目に見えて減ります。なぜ重要かというと、注文が急に増える波(繁忙の波動)にも、少人数で安定して対応できるからです。もちろん初期費用はかかりますが、動かす商品数や1日の出荷量が多いラインだけに部分導入するなど、効果の大きいところから始めれば投資回収が現実的になります。結果として、処理時間のばらつきが小さくなり、出荷締め切りに余裕が生まれます。
-
バーコード・音声・ハンディ端末の活用
バーコードは「これは正しい商品か」をその場で確認できる道具です。ハンディ端末(携帯型のスキャナ付き小型端末)で商品や棚のバーコードを読み取ると、端末が正誤を即時に知らせ、在庫数も自動で更新されます。音声ピッキングはヘッドセットで指示を聞き、作業者が声で確認数字を返す方式で、両手が空くため重い荷物も安全に扱えます。現場がこれらを使うと、人の記憶や勘に頼らずに作業でき、ミスが減るだけでなく、あとから「誰が・いつ・何を取ったか」を追跡(トレーサビリティ)できます。これが重要なのは、教育期間を短くできることと、在庫のズレを防げることです。新人や日本語に自信がないスタッフでも、数字とスキャンで共通のやり方に統一でき、検品と在庫更新が同時に進むため、締め作業も軽くなります。
小さな工夫の積み重ねが、大きな時短と品質向上につながります。次の章では、これらの仕組みを現場に根づかせるための運用ルールと改善サイクルの作り方を見ていきましょう。
ピッキングにおける課題|ミス・歩行距離・人材不足をどう克服するか
「ピッキング、なぜ昨日は順調だったのに今日は遅れるのだろう?」そんな小さな違和感を、あなたは現場で何度も感じていないでしょうか。セール直後に注文が一気に増えて、棚の前で立ち止まる時間がじわじわ伸び、残業とミスが増える——その裏側には、見過ごしがちな課題がいくつも潜んでいます。ここでは、ピッキングの代表的な課題を3つに整理し、なぜそれが重要なのかを具体例とともに解きほぐします。

作業ミスの発生要因
たとえば、同じデザインでサイズだけ違うTシャツや、似たパッケージの化粧品が並ぶ棚で、急いでいるスタッフが1つ取り違える。指示書の更新が遅れて、在庫のロケーション(置き場所)の表示と実物がずれる。バーコードの読み取りを省略して目視で確認した結果、色番が違うまま進んでしまう。こうした「よくある」ミスは、単純作業の繰り返しによる注意力の低下や、表示の見づらさ、工程の複雑さが重なって起きます。
このミスが重要なのは、誤出荷が1件でも発生すると、返品対応・再出荷・問い合わせ対応が連鎖し、コストと時間が二重三重に膨らむからです。特にECではレビューやSNSでの評価に直結し、ブランドの信頼まで損ないます。対策は難しく見えて、実は「人の判断に頼る場面を減らす」ことが核心です。たとえば、バーコード照合の必須化や、商品画像付きのデジタル指示、類似品の離隔配置、検品の前倒し(ピッキング時に同時検品)などです。
人手不足と人件費の高騰
朝、欠員が2人出たことで、1人が3役を担い、棚入れ(補充)とピッキングが競合して通路が渋滞する——そんな日が続くと、生産性は一気に落ちます。採用が難しく、最低賃金も上がる中、場当たり的に人を増やすだけでは追いつきません。新人の習熟にも時間がかかり、教育コストが隠れた負担になります。
だからこそ、仕組みで人の負荷を平準化することが重要です。歩く距離を減らすためにオーダーをまとめて取る「バッチピッキング(まとめ取り)」や、エリアごとに担当を分ける「ゾーンピッキング(区分け方式)」を取り入れると、欠員の影響を小さくできます。さらに、倉庫管理システム(WMS)とハンディ端末で動線を自動生成すれば、経験差によるばらつきも縮まります。人に頼るのではなく、仕組みに頼れる状態をつくることが、コスト高の時代の防衛線です。
作業環境による生産性の差
同じメンバーでも、明るくて見やすい表示がある通路では早く正確に進み、暗くて狭い通路では立ち止まる回数が増えます。棚の高さが合っていないと、かがむ・背伸びする動作が増え、1日あたりの歩数や動作が積み上がって疲れとミスにつながります。実際、ピッキング時間の多くは「歩く」と「探す」に費やされます。
この差を埋める鍵は、環境そのものを最適化することです。手の届きやすい高さに出荷頻度の高い商品を置く「ゴールデンゾーン配置」、よく売れる順にA・B・Cで分ける「ABC分析(売れ筋ごとに置き場を変える考え方)」、大きな文字と色分けによる場所表示、十分な照明と夏場の冷却対策などは、即効性が高い施策です。環境を整えると、ベテランの勘に頼らずに新人でも同じ成果を出しやすくなり、安全性も向上します。
ピッキングの課題は、人の注意の限界、人数の揺らぎ、そして環境の設計不良が絡み合って起きます。次の章では、これらを現場でどう改善し、数値で成果を出すか——具体的な改善ステップとツールの選び方を紹介します。
ピッキングの最新動向|ロボット・音声・ウェアラブルの導入事例
「うちの倉庫、最近のトレンドに追いつけているのだろうか?」と感じたことはありませんか。たとえば出荷が集中する夕方、担当者が棚と棚のあいだを何千歩も歩き回る光景は、今や少しずつ変わりつつあります。人が棚に行くのではなく、棚や箱のほうから人に近づいてくる——そんな現場が増えているのです。

ロボットやAGVの導入事例
最近の現場では、AGV(無人搬送車)やAMR(自律走行ロボット)が棚やトート(樹脂箱)を作業者の前まで運ぶ「Goods-to-Person方式」が広がっています。たとえばアパレルや日用品のセンターでは、導入後に歩行距離が3〜5割減り、ピッキングの手元作業に集中できるようになった事例が報じられています。加えて、カメラとセンサーで手の動きを確認する仕組みや、表示灯で取り間違いを防ぐ「デジタルピッキング(ライトで指示)」も組み合わせることにより、ミス率が下がる現場もあります。これは人手不足や「2024年問題」(ドライバーの残業規制で物流全体の余裕が減る課題)に直面するなか、限られた人数で出荷量を守るために重要です。新人教育の時間が短くなることもポイントで、操作が直感的なロボットは早く戦力化できるからです。導入の狙いを整理すると、次のようになります。
- 歩行の削減により、1時間あたりのピック数を底上げする
- 取り間違いを減らし、返品や再作業のロスを抑える
- 作業者の負担を軽くし、離職を防いで安定稼働につなげる
AIによる需要予測と効率化
AIは、過去の受注データや天気、キャンペーン情報から「いつ、何が、どれくらい売れるか」を予測します。たとえば梅雨入り前にレインコートの注文が増える傾向をとらえ、前日に前倒しで補充したり、出しやすい棚に前寄せしたりします。さらに、AIはABC分析(よく出る順に商品を3ランクに分ける考え方)を自動で更新し、Aランク商品を作業者の近くに集め、ピッキングの順番やルートも無駄が出ないように並べ替えます。これが重要なのは、欠品や過剰在庫を減らしつつ、出荷リードタイム(注文から出荷までの時間)を短くできるからです。繁忙と閑散の波にあわせて人員配置を変える「波動対応」も精度が上がり、残業や待ち時間のムダが目に見えて減ります。
サステナビリティと省エネの観点
省エネは、いまやコスト削減だけでなく取引先からの評価にも直結します。照明をLEDに変えるだけで消費電力は一般に3〜5割下がり、通路を短くするレイアウトとロボット搬送を組み合わせれば、人の移動エネルギーと稼働時間を同時に減らせます。紙のリストをなくす「ハンディ端末」や「音声ピッキング(耳元の指示で作業)」は、用紙代や廃棄物を減らし、手元がふさがらないので安全性も上がります。さらに、電動フォークリフトや再生可能電力の活用は、サプライチェーン全体のCO2排出を下げ、環境目標に敏感な顧客から選ばれる理由になります。なぜ重要かというと、環境配慮は長期のコストを下げつつ、入札や取引条件での「必須項目」になりつつあるからです。
最新動向の共通点は、「人が強みを発揮する作業に集中し、機械とデータで移動と待ちを削る」ことにあります。
ピッキング:よくある質問
まとめ|ピッキングを理解して物流効率を高める
ピッキングの改善は、単なる現場作業の効率化にとどまりません。正しい商品を正しいタイミングで届けることは、顧客の信頼を積み重ね、企業の競争力を左右する基盤です。動線を見直して無駄な歩行を減らすこと、バーコードやデジタル指示を導入して取り違えを防ぐこと、人員配置を計画的に行うこと――こうした一つひとつの工夫が、残業や突発的な外注費を抑え、安定した出荷体制を支えます。

さらに、最新技術を取り入れることで、ピッキング精度とスピードは一段と高められます。SBSリコーロジスティクスでは物流技術部門(LTチーム)が、「自動倉庫」「ソーター」「デジタルピッキングシステム」など、ピッキング作業そのものを効率化・自動化するマテハン機器の設計・導入を支援しています。たとえば、デジタルピッキングシステムによるランプの点灯や音声指示は、取り違いを防ぎ、新人でもすぐに現場に馴染めるようになります。こうした仕組みは、まさにピッキングを現場改善の起点に変える技術です。
まずは日常の改善を積み重ね、小さな成功を確実に重ねながら、技術の力で一歩先のピッキングへ進化することが大切です。SBSリコーロジスティクスは、現場の課題を共有しながら、ピッキング改善を含めた物流全体の最適化をパートナーとして支えます。
SBSリコーロジスティクスの物流サービス
SBSリコーロジスティクスでは、BtoB配送に特化した高品質な物流サービスを提供しています。精密機器から通販物流まで、信頼と柔軟性を兼ね備えたトータル物流ソリューションをお探しの方は、ぜひこちらから詳細をご覧ください。
- 3PLとは? 意味や導入メリット、事業者選びのポイントなど解説
- サプライチェーンとは? 意味や具体例を交えて徹底解説
- ロジスティクスとは? 物流との違いや課題・今後など徹底解説
- 物流とは? 機能や効率化メリット、ロジスティクスとの違いなど解説
- 物流センターとは? 役割や種類、メリット・最適化についてなど解説
- 物流倉庫とは? 役割や種類、メリット・最適化についてなど解説
- 保管とは? 物流における保管について徹底解説
- キッティングとは? 作業内容やサービス選定のポイントなど徹底解説
- WMSとは? サプライチェーンを変革する、倉庫管理システムの力
- WESとは? 倉庫運営の効率化と自動化を実現するシステムを解説
- WCSとは? 倉庫運営を変革するWCSの全貌
- ラストワンマイルとは? 顧客接点となる、物流のラストワンマイルの重要性とその未来
- 2024年問題とは? 基礎知識、その影響や対応策、そして今後の展望など解説
- 運送会社とは? 役割と種類・分類、DX事情、選ぶポイントなどを解説
- リードタイムとは?意味・計算方法・短縮事例を徹底解説
- 送り状とは? 種類・作成方法・電子化まで徹底解説
- 棚卸とは? 物流現場での意味・手順・課題・改善策を徹底解説
- ロットとは? 物流における基本意味・使われ方・管理の重要性をやさしく解説
- SKUとは何か? 意味・目的・設計・管理・ツール・最新動向まで徹底解説
- ピッキングとは? 意味・種類・効率化の工夫をわかりやすく解説