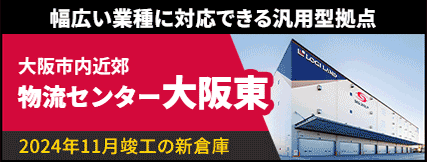SKUとは何か?
意味・目的・設計・管理・ツール・最新動向まで徹底解説
Tシャツの白Mと黒L、在庫が混ざって困ったことはありませんか?SKUとは色やサイズごとに商品を見分ける番号のことです。SKUが分かれば棚卸や欠品防止、ECと店舗の在庫同期がぐっと楽になります。ここではSKUの意味とJANとの違い、具体例、設計と運用のコツ、ツール選び、失敗回避をやさしく解説します。

- SKUとは?基本的な意味と定義|基礎概念とJAN・バーコードとの違いを整理
- SKUを使う目的|在庫精度向上・分析・顧客満足にどう効くか
- SKUの具体例|色やサイズ別の分け方からアパレル・ECの実例
- SKUと似た用語との違い|JAN・商品コード・型番との使い分け
- SKU設計の基本ルール|桁数・命名・拡張性を考えた設計の勘所
- SKU管理の実務ポイント|マスタ運用、在庫同期、棚卸・発注点の連携
- SKU導入のメリット・デメリット|可視化の効果と複雑化のリスク、対策
- SKUよくある失敗と回避策|重複・移行ミス・廃番対応の落とし穴を避ける
- SKU:よくある質問
- まとめ|SKUを正しく理解して在庫と販売を強くする
SKUとは?基本的な意味と定義|基礎概念とJAN・バーコードとの違いを整理
在庫の呼び方がバラバラで、現場とEC担当の会話がかみ合わない。そんな経験はありませんか?どれが「同じ商品」で、どれが「別物」か、日々の業務で迷うことは多いはずです。SKUとは、色・サイズ・容量などの違いごとに商品を区別し、在庫を数えたり販売を追跡したりするために、自社が付ける管理用の最小単位です。難しく聞こえますが、要するに「在庫を数えるときのひとまとまり=商品バリエーションごとの番号(ラベル)」だと考えてください。

SKUの正式名称(Stock Keeping Unit)
SKUの正式名称はStock Keeping Unitです。Stockは在庫、Keepingは保持・管理、Unitは単位という意味で、直訳すると「在庫を管理するための単位」になります。小売やEC、物流の現場では、SKUを使って入庫・出庫・棚卸・販売分析を同じ切り口でそろえます。SKUは国や業界が決める共通コードではなく、各社が自社運用に合わせて設計する社内基準のコード(識別子)です。
企業がSKUを明確にすることは、現場とバックオフィス、店舗とEC、さらには倉庫と仕入先の認識をそろえるうえで重要です。SKUが曖昧だと、白TシャツMと白TシャツLを同じ在庫として数えてしまい、欠品や過剰在庫が起こります。逆にSKUが整理されていると、どのサイズが売れているかを日次で把握でき、補充やセール判断が早くなります。結果として、欠品率の低下や在庫回転の改善につながります。
SKUの日本語での意味
日本語では、SKUは「在庫管理上の最小単位」や「アイテム単位」と呼ばれます。たとえば同じTシャツでも、白・M、白・L、黒・Mはそれぞれ別のSKUです。飲料なら500mlと1.5L、箱入りとバラ売りは別SKUになります。あなたがコンビニで「ツナマヨのおにぎり」を2個買うとき、味や容量が同じなら同一SKU、具が変われば別SKUというイメージです。
この考え方が重要なのは、在庫を正しく数える軸が決まるからです。仕入・棚卸・返品・分析のすべてがSKUでひとつにそろうと、月末だけでなく毎日の売れ行きから素早く発注量を調整できます。ECでは、同じ商品ページでも色やサイズごとの在庫・売上を見ることで、人気バリエーションを優先補充できます。結果として、売り逃し(機会損失)や余剰在庫の発生を抑えられます。
JANコードやバーコードとの違い
JANコード(Japanese Article Number)は、主に日本国内流通で使われる標準商品コードで、一般的には13桁(または8桁)です。メーカーやブランドが発行するもので、同じ商品バリエーションであればどの店舗でも同じJANが使われます。一方、バーコードは「黒い縞の機械読取記号」の総称で、JANはバーコードの一種です。つまり、バーコードは見た目・表現方法のこと、JANはその中身(標準コード)のことだと考えてください。
SKUはこのどちらとも違い、各社が自分たちの運用に合わせて決める社内コード(識別ラベル)です。多くの場合、1つのSKUは1つのJANに対応しますが、セット品や自社限定の詰め合わせのように、JANが存在しないSKUを運用する場面もあります。逆に、輸入品で同じJANでも自社では出荷単位を分けたい場合、SKUを複数に分けて管理することがあります。
この違いを理解することは、システム連携や倉庫指示のミス防止に直結します。店舗のスキャナーはJANを読み取り、基幹・在庫システムはSKUで在庫を持つ、といった役割分担を決めることで、読み取りやすさと運用の柔軟さを両立できます。もしJANとSKUを混同すると、受発注データがずれて、倉庫に別物が届く、棚卸で合わないといったトラブルが起こります。
まとめると、SKUは自社の在庫を正しく数えるための最小単位で、JANやバーコードは外部と情報を合わせるための標準コードとその表現です。
SKUを使う目的|在庫精度向上・分析・顧客満足にどう効くか
「在庫数が合わない」「どの商品が利益を生んでいるのか分からない」「人気サイズがすぐ欠品する」――店舗やECでよく聞く悩みではないでしょうか。実は、これらはすべてSKUの運用によって改善できます。SKUを使うことで、在庫管理の効率化、販売・利益分析、顧客満足度の向上という3つの目的を同時に実現できるのです。ここからは、その具体的な効果を一つずつ見ていきましょう。

在庫管理の効率化
「在庫数が合わない」「同じTシャツなのに色で数がズレる」そんな悩みはありませんか。あなたの店舗が、白TシャツMと黒TシャツLを1つの「Tシャツ」として数えるのではなく、SKUで分けて数えるだけで、数え違いと探し回りがぐっと減ります。現場ではSKUをバーコードや棚番(ロケーション)とひも付けてピッと読み取るだけにすることで、手書きのチェック表よりミスが減り、棚卸のスピードも上がります。多くの小売・EC現場で、手作業と比べてピッキングミスが3割以上減り、棚卸時間が半分以下になったという声がよくあります。これは、SKUごとに置き場所と数量が明確になることで、誰が作業しても同じ結果になりやすく、確認の二度手間が減るからです。
販売・利益分析への活用
「どの商品が本当に利益を生んでいるのか」を直感に頼らず言い切れることが、仕入れと販促の強さになります。SKUごとに売上と在庫、仕入原価を持っておくと、色やサイズ単位の売れ筋・死に筋がはっきり見えます。たとえば、スニーカーの黒27cmだけが回転(在庫が売れて入れ替わるスピード)が早いのに、他サイズを大量発注してしまう失敗を避けられます。分析で見る基本は次のようなものです。
- 販売点数・売上金額(SKUごとの売れ行き)
- 在庫回転日数(何日で在庫が1周するか)
- 粗利率(売上から仕入原価を引いた利益の割合)
これらをSKUで比較することにより、値下げが必要な在庫、広告をかけるべき在庫、発注を止めるべき在庫が具体的に判断できます。重要なのは、店舗がお金を生むのは「商品全体」ではなく「SKU単位」であるという事実です。SKUまで掘り下げるからこそ、無駄な在庫に現金が寝るのを防ぎ、限られた仕入れ枠を勝ち筋に集中できます。
顧客満足度の向上と欠品防止
お客様が「欲しいサイズがいつも品切れ」「注文後に在庫切れ連絡が来た」と感じると、二度と戻ってこないことがあります。SKU運用をすると、どのSKUがどのくらいの頻度で売れるかが読めるため、需要予測と安全在庫(急な注文に備えた予備)の設定がしやすくなります。たとえば、毎週末にだけ伸びる人気色のニットをSKUデータで把握できれば、木曜に前倒しで補充し、欠品を防げます。また、入荷予定日をSKUごとに商品ページへ表示したり、在庫が薄い時に代替SKUを提示したりすることで、購入機会を逃しにくくなります。さらに、SKUとロケーションをひも付けたピッキングは発送の取り違えを減らし、返品や問い合わせの件数を下げます。欠品率が下がり、発送ミスも減ることで、配送リードタイムが安定し、レビュー評価やリピート率の改善につながります。これは、顧客が「この店は欲しい時に確実に届く」と信頼できるからです。
まとめると、SKUを使う目的は在庫の見える化と意思決定の精度を同時に高めることにより、売上と満足度を底上げすることなのです。次では、効果を最大化するためのSKUの付け方や運用ルールを、実例を交えて紹介します。
SKUの具体例|色やサイズ別の分け方からアパレル・ECの実例
「同じ商品なのに、色やサイズが違うと在庫の扱いはどう変わるのだろう?」と迷ったことはありませんか。あなたが店舗やECで在庫を数えるとき、実は「SKU(在庫管理上の単位=商品)」が鍵になります。

同一商品でSKUが分かれる条件(色・サイズ・容量・セット数)
あなたが白TシャツのMとL、黒TシャツのMとLを扱うとき、それぞれは別のSKUになります。色やサイズが違えば、お客様が選ぶ商品が実質的に別物だからです。食品や日用品でも同じで、シャンプーの500mlと詰め替え350ml、2本セットはそれぞれ個別のSKUになります。さらに、容量違い・香り違い・限定パッケージなどのバリエーションもSKUを分けます。これは「入荷数・売れ方・保管場所・賞味/消費期限」が異なり、同じ箱で数えると欠品や過剰在庫を招くためです。SKUを条件ごとに分けることで、あなたは色別・サイズ別の売れ筋や在庫偏りを正しく把握できます。その結果、発注数を無理なく調整でき、棚卸やピッキング(商品の取り出し)での取り違いも避けられます。
アパレルのSKU設計例
あなたがTシャツ型番「TS001」を扱うとして、「TS001-WH-M(白・M)」「TS001-BK-L(黒・L)」のように「型番-色-サイズ」でSKUコードを作るのが一般的です。例えば白S/M/Lと黒S/M/Lなら合計6SKUになり、さらに限定色を加えるとSKU数は一気に増えます。ECでは「親商品=TS001」「子=各色各サイズ」という親子構造にして、1つの商品ページで色・サイズを選べる形にすると管理と表示がスムーズです。こうした設計が重要なのは、あなたがサイズ別の回転率や色別の在庫偏りをすぐに見極め、値下げや再発注の判断をタイムリーにできるからです。店舗とECの在庫を連動させるときも、同じSKUコードでそろえておけば、引当(注文分の取り置き)や店舗間移動が迷いなく進みます。
ECサイトのSKU表示・在庫連携の例
あなたがECの商品ページで色とサイズをプルダウンで選ぶとき、裏側では各選択肢がそれぞれのSKUに紐づいています。「残り3点」「在庫なし」「お取り寄せ」といった表示もSKU単位で制御されます。倉庫側ではWMS(倉庫管理システム)とOMS(受注管理システム)がSKUコードでつながり、入荷・検品・出荷までを一気通貫で更新します。バーコード(JAN/EAN)をSKUに割り当て、あなたがスキャンして出荷すれば、色違い・サイズ違いの誤出荷を防げます。これが重要なのは、在庫ズレや売り逃しを最小化し、広告やクーポン施策の効果測定もSKU別に正確にできるからです。実務では次のような利点があります。
- 売れ筋SKUだけ自動で在庫アラートと補充依頼を出せる
- 欠品SKUを非表示・予約販売に切り替えて機会損失を減らせる
- 返品もSKU単位で再販可否を判断できる
SKUを色・サイズ・容量・セット数で丁寧に分け、アパレルでは「型番-色-サイズ」の親子構造にし、ECではシステム連携まで一気通貫にすることが、正確な在庫と売上最大化の近道です。
SKUと似た用語との違い|JAN・商品コード・型番との使い分け
レジで読み取るバーコードと、社内で使う「SKU(在庫管理上の単位=商品)」は何が違うのかと迷ったことはありませんか。ECや店舗運営で言葉を混同すると、発注や在庫が一気にややこしくなるので、ここで整理しておきましょう。

SKUとJANコードの違い
あなたが倉庫で数える「SKU」は、会社や店舗が独自に決める在庫の最小単位です。たとえば同じTシャツでも、色やサイズごとに「白M」「白L」「黒M」と別々のSKUになります。一方で「JANコード」は、GS1が管理する流通共通の識別子で、レジや仕入れで使う13桁(または8桁)のバーコードです。メーカーが色やサイズごとに別JANを付けることが多い一方、店舗独自のセット商品や福袋にはJANがないこともあり、その場合は店舗がSKUだけで管理します。
この違いが重要なのは、現場で使うシーンがはっきり分かれるからです。POSや取引先とのデータ連携にはJANが必要ですが、棚卸やピッキング、保管場所の割り当てはSKUで動きます。もしSKUとJANの対応表(マスタ)を用意しないと、同じ商品を二重に登録して在庫がズレたり、JANのないセット品が永遠に在庫ゼロのままになったりします。要点は次の2つです。
- JAN=社外と通じる共通コード、スキャンして売買をつなぐ
- SKU=社内で数える管理単位、現場オペレーションの基準
SKUと商品コード(社内コード)の違い
会社が台帳やシステムで使う「商品コード(社内コード)」は、番号そのものの名前で、SKUという“概念”を表すために会社が付ける識別子です。つまり、SKUが「数える粒度」の考え方で、商品コードはそれに貼る“番号札”です。会社によっては、親子構造にして「商品コード=親(Tシャツ)」と「SKUコード=子(白M/白L…)」に分けることもありますし、逆にSKUと商品コードを同一の番号で運用する会社もあります。
ここを曖昧にすると、基幹システムやEC、会計の間で品目が合わず、移行や棚卸で混乱します。あなたが「発注は親コード、在庫はSKUコード」というルールを事前に決めれば、入出荷・売上・原価が一本の線でつながります。特にモール出品や複数倉庫を使うとき、商品コード=社内共通言語、SKU=現場の作業単位と整理しておくことが、誤出荷や欠品の防止につながります。
SKUと型番・品番の違い
「型番・品番」はメーカーが製品仕様を示すために付ける番号で、見積もり、問い合わせ、保証書で使われます。家電の「XYZ-100-W(W=白)」のように、記号で色や年式を示すこともありますが、流通の都合で同じ型番でもセット内容が異なるケースや、販売店限定セットで型番が存在しないケースもあります。その場合、あなたはSKUや社内コードで管理するしかありません。
重要なのは、仕入れ・保証の会話は型番で、在庫・棚配置・ピッキングはSKUで進むという点です。型番だけで現場を動かすと、同型番の色違いやセット違いを見落として誤出荷が起きます。逆にSKUだけで仕入れ先と話すと通じないため、型番とJAN、SKU(社内コード)を1対1または1対多で正しく紐づけることが、日々の発注精度とサポート対応の速さを左右します。
まとめると、JANと型番は「社外と通じる共通の言葉」、SKUと商品コードは「社内で作業を回すための言葉」です。
SKU設計の基本ルール|桁数・命名・拡張性を考えた設計の勘所
サイズや色違いの商品が増えるほど、品番管理がごちゃついていませんか?伝票やラベルで見た目は回っていても、後から検索や棚卸しで苦労することはありませんか。SKU(在庫管理上の単位=商品)を最初にどう設計するかで、毎日のミスと手戻りは大きく変わります。

桁数・構成ルールの決め方
SKUは「固定の桁数」と「並べ方(構成)」をあらかじめ決めておくことが基本です。例えば「ブランド2桁-カテゴリ2桁-型番3桁-色2桁-サイズ2桁-連番3桁」といった具合に、意味のあるブロックを組み合わせ、全体を12〜16桁程度に収めると見やすく、システム処理も安定します。設計の際には、社内システムが扱える桁数や、伝票・ラベルの印字スペース、利用するバーコード(JANやCode128など)の文字数制約を必ず確認することが重要です。特に意識すべきポイントは以下の通りです。
- 考慮すべき点:システムの最大桁数/禁止文字、ラベルの印字幅、将来のバリエーション数
- 固定長にする理由:並びや桁揃えで検索・抽出・ソートが簡単になるため
- 0埋めの推奨:「3」ではなく「003」にして桁のブレを防ぐため
こうしたルールを定めておくことで、SKUが100や1000を超えても「一文字違い」に気づかずミスするリスクを減らせます。固定長とブロック構成が整っていれば、倉庫での読み上げやExcelでのフィルタリング、WMS(倉庫管理システム)での一括検索が一気に楽になり、入出荷や棚卸の精度向上にもつながります。
人が読める/機械が扱いやすい命名のバランス
現場では「黒のMね」と人がパッと見て分かることが大切ですが、システムは「決まった形式でブレなく扱える」ことを優先します。この両立のために有効なのが、「人向けの見やすい表記」と「機械向けのシンプルな表記」を分ける方法です。例えば、登録データはシステム処理に適した「記号なし・大文字・固定長」とし、ラベルや帳票は読みやすいように「区切り(ハイフン)を入れる」形式にします。
- データ登録用:BLTS123BKM
- ラベル/帳票用:BL-TS-123-BK-M
さらに、次のようなルールを徹底すると効果的です。
- 登録は「記号なし・固定長」、表示は「ハイフン区切り」
- 紛らわしい文字は使用禁止(例:Oと0、Iと1、Sと5)し、大文字に統一
- 先頭の0を保持し、桁ズレやソート崩れを防ぐ
こうした区別が重要なのは、ヒューマンエラーの多くが「似た見た目」や「桁数のブレ」によって起きるからです。ピッキング現場では一瞬で識別できる表記が作業スピードを上げる一方、EDI(データ連携)やシステムへの取り込みは、余計な記号があると失敗の原因になります。つまり、人の目に優しい表記と機械処理に適した表記を使い分けることが、正確さと効率を両立させる鍵なのです。
将来の拡張性(バリエーション増)への配慮
SKUは最初に設計したときのままでは済まないケースが多くあります。今は「色×サイズ」だけでも、来季には「素材」「限定色」「セット商品(2点組)」などが加わり、SKUの数は一気に増えていきます。そのため、最初から「増える前提」で設計することが大切です。
実務では、SKUコードの中に2〜3桁の拡張枠をあらかじめ用意する、または派生を示すサフィックス(末尾コード)を設けると安心です。例えば現時点では「00」を入れておき、将来「01=素材A」「02=限定色」と割り当てれば、既存SKUを変えずに拡張できます。Tシャツ(白/黒×S/M/L)で6SKUだったものが、素材が加わると12SKU、季節色が加わると18SKU…といった変化にスムーズに対応できるわけです。
押さえるべきポイントは以下の通りです。
- 拡張枠を2〜3桁確保し、当面は「00」とダミーで埋めておく
- 派生はサフィックス(末尾コード)で表現し、元の型番は変えない
- 付帯情報(素材・季節など)はマスタの別項目に保持して整理
拡張性を意識することが重要なのは、一度配ったSKUを後から変えると、棚番や発注履歴、返品対応、分析データまで影響が及ぶからです。SKUを途中で変更するのは大きな手間と混乱を招きます。逆に、初期設計で余白を残しておけば、商品ラインが広がっても無理なく運用を続けられます。次の章ではこのSKUを現場で生かすためのラベル設計や棚番との紐づけのコツを紹介します。
SKU管理の実務ポイント|マスタ運用、在庫同期、棚卸・発注点の連携
SKU(在庫管理上の単位=商品)が増えるほど、どこに何があるか分からなくなっていませんか。EC・実店舗・倉庫で数字がそろわず、毎回つじつま合わせをしていませんか?

マスタ管理と運用フロー
SKUが増えてくると、「名前だけ違う同じ商品」や「バーコードが重複した商品」が登録されてしまい、在庫や受注でトラブルが起きやすくなります。これを防ぐための土台がSKUマスタ(商品情報の台帳)です。
マスタには、商品コード・規格(色やサイズ)・バーコード・単位(1個/1箱)・寸法や重量・賞味期限やロット・セット商品の内訳・販売/仕入のステータスなど、商品に関するすべての情報を登録します。そして、この登録作業にはルールを設けることが重要です。
たとえば:
- 申請:現場担当者が新しいSKUや変更内容を申請
- 承認:在庫責任者が内容をチェック
- 登録・配信:システム担当者がSKUマスタに反映し、ECや会計など他のシステムへ連携
このように廃番や変更も同じ流れで扱い、履歴を必ず残すようにすると、「いつ・誰が・なぜ」SKUを更新したか追跡でき、後から混乱しません。
なぜこれが重要かというと、SKUマスタは WMS(倉庫管理システム)、ECサイト、会計システムの共通の“鍵” だからです。どこか一つでも表記ゆれやコード違いがあると、受注が止まったり、ピッキングで間違いが起きたりします。実務では、登録前にテスト環境で入出庫をシミュレーションし、ラベル印字やスキャナー読み取りを確認すると、現場トラブルを大幅に減らせます。
倉庫・実店舗・ECの在庫同期
次に、倉庫・実店舗・ECの在庫を同じ数に保つ仕組みが必要です。これができていないと、「売れたのに在庫がない」「実際には売れない商品を販売してしまった」といったトラブルが発生します。
在庫同期の基本は、受注が入った瞬間に「引当済み」(売る分を確保)、出荷で「引落し」、返品で「戻し」という一連の動きをシステムに正しく反映することです。これをAPI(システム同士のリアルタイム連携)やCSV連携で各システムへ伝えます。リアルタイム更新が難しい場合でも、「増減があった時だけ送る」仕組みを導入すれば、負荷を抑えつつデータの鮮度を上げられます。
実務では、セール時などに一気に在庫が減るケースが要注意です。土曜夜のタイムセールのように注文が集中すると、在庫反映が10〜15分遅れただけで過剰販売につながることがあります。
こうした事故を防ぐには、予約や取り置きがある場合に「販売可能在庫」と「予約在庫」を分けて管理・表示することが大切です。さらに、EC側で「在庫が一定数を下回ったら自動で販売停止にする」閾値設定を行うと、安全弁として機能します。
棚卸・発注点管理との連携
最後に、棚卸と発注点を連動させることで在庫を安定させることができます。 年に一度の一斉棚卸だけでは差異が大きくなりやすく、気づいたときにはすでに手遅れになってしまうこともあります。そこで、毎日や毎週に一部のSKUだけを数える「循環棚卸」を取り入れると、差異を早い段階で発見できます。
差異が見つかった場合は、大きく3つに分類して原因を追うと分かりやすいです。
- マスタ不一致:SKUの登録内容が実際と違う(例:1箱=12個と登録しているのに実物は10個入り)
- 入出庫ミス:受け入れや出荷でスキャン漏れや数量の数え間違いがあったケース
- 破損やロス:商品が破損・廃棄されたり、盗難などで物理的に減ってしまったケース
こうして原因を切り分け、根本から修正していくことで差異を減らすことが出来ます。
次に、発注点の考え方です。基本式はシンプルで、平均の売れ行き × 仕入リードタイム(日数) + 安全在庫で求められます。安全在庫は「売れ行きのばらつき」と「どれだけ欠品を避けたいか」という方針から決めます。例えば1日平均5個売れ、仕入に7日かかるなら、発注点は「35個 + 安全在庫」となります。さらに、棚卸で差異が多いSKUは「不安定な商品」と見なして安全在庫を厚めにし、逆に差異が少なく安定しているSKUは薄めに設定すると効率的です。
要するに、SKUマスタを正しく整え、在庫同期で数字を合わせ、棚卸と発注点を結びつけて回すこと。これが欠品と過剰在庫を同時に減らす一番の近道です。
SKU導入のメリット・デメリット|可視化の効果と複雑化のリスク、対策
SKUは現場を効率化する強力な仕組みである一方、導入や運用の仕方によっては思わぬ落とし穴もあります。ここではSKUを導入することで得られるメリットと、運用が複雑化することによるデメリット、そしてそれを防ぐための具体的な対策について解説します。

メリット:可視化と生産性向上
店舗や倉庫で「白いTシャツのMサイズ」と「白いTシャツのLサイズ」を別々のものとして数えるのがSKU(在庫管理上の単位=商品)です。SKUを導入すると、色・サイズ・型番ごとに在庫数と売れ方が見える化されます。例えば、同じ白TでもMが在庫5でLが在庫0と分かれば、担当者はすぐに補充や発注を判断できます。これは現場の迷いを減らし、欠品や過剰在庫を防ぐうえで役立ちます。
SKUごとの見える化は作業の速さにも効きます。担当者が棚番とバーコードでピンポイントに探せるようになるため、ピッキング(出荷のための商品集め)や補充が短時間で終わります。社内事例や一般的な在庫管理システム(WMS:倉庫管理システム)の導入例では、SKU別の棚割りとバーコード運用でピッキング時間が20〜30%短縮し、誤出荷が半分以下になったケースもあります。作業が速く正確になると、同じ人数でも出荷件数を増やせます。
これが重要な理由は、在庫と作業の「ムダ」を具体的に減らせるからです。見える化により、売れ筋と動かない商品(死に筋)が分かれ、資金を寝かせる在庫を減らせます。その結果、現金が回りやすくなり、欠品が減って顧客満足も上がります。
デメリット:SKU肥大化による複雑化
一方で、SKUを細かく分けすぎると数が一気に増えます。例えば、色10×サイズ5×型番2で100SKUになり、棚は細かい区画だらけになります。担当者は場所を覚えにくくなり、歩く距離も増え、入荷・保管・補充のどこかでミスが起きやすくなります。さらに、マスタ(商品情報)の登録や価格・JANのメンテナンスも手間がかかります。
多くの現場では、売上の8割を上位2割のSKUが占める「80:20」の傾向があります。つまり、あまり動かないSKUが大量に棚を占有し、発注ロットの端数や保管スペースのムダを生みます。結果として、在庫が多いのに欲しいサイズだけ欠ける「品切れと過剰在庫の同時発生」が起きがちです。これはキャッシュフローを圧迫し、値下げや廃棄のリスクも高めます。
このリスクが重要なのは、SKUの増加がそのまま現場の複雑さとコストに直結するからです。SKUが増えるほど探す・覚える・登録する作業が増え、教育にも時間がかかります。複雑さが増すと、人ががんばるだけでは吸収しきれず、遅延や誤出荷につながります。
対策:標準化と定期的な棚卸
SKUのメリットを活かしつつ複雑化を抑えるには、「標準化」と「棚卸(数合わせ)の仕組み化」が効きます。まず、SKUの命名・ラベル・棚番のルールを決めます。例えば「ブランド-型番-色-サイズ」の順で統一し、すべてにバーコードやQRを貼り、棚にも同じ情報を表示します。WMS(倉庫管理システム)がない場合でも、表計算とハンディスキャナで同様の運用は可能です。標準があると新人でも迷わず、探す時間と登録ミスが減ります。
次に、SKUの優先度をABC分類(よく売れるA、普通のB、あまり動かないC)に分けます。Aは出荷口の近くに置き、補充の頻度を高めます。Bは通常運用、Cは保管場所を奥にして在庫を絞ります。実務では、Aは週1回、Bは月1回、Cは四半期に1回の循環棚卸(毎日少しずつ数える方法)を回すと、在庫差異率(帳簿と実数のズレ)が1%から0.3%程度まで下がることがあります。ズレが早期に見つかると、紛失や誤格納の再発を抑えられます。
最後に、SKU自体を見直す仕組みを入れます。3カ月連続で動きがないSKUは発注停止、6カ月で廃番候補にするなどの基準を決め、営業と相談して統合や絞り込みを進めます。現場では、色を減らす、サイズ展開を見直すなどの小さな決断が、歩行距離や棚スペースの大幅な削減につながります。これにより、SKUの見える化のメリットを保ちながら、肥大化のリスクを抑えられます。
SKUの導入は在庫と作業を見える化して生産性を上げますが、放置するとSKUが増えすぎて現場が複雑になります。標準化と定期棚卸、そしてSKUの定期的な見直しを行う事でメリットを最大化しデメリットを最小化できます。
SKUよくある失敗と回避策|重複・移行ミス・廃番対応の落とし穴を避ける
同じ商品なのに呼び方やコードがバラバラで、現場が迷っていませんか。型番の変更や販売終了のたびに、在庫やページ更新が追いつかず、機会損失が出ていないでしょうか。

意味の重複・例外ルールだらけ
例えば、色の表記が「黒/ブラック/BK」、サイズが「M/ミディアム/中」と混在すると、担当者は検索でヒットさせにくくなり、倉庫ではピッキングの取り違えが起きやすくなります。さらに「このブランドだけ別ルール」などの例外が増えると、新人が覚えることが増え、問合せ対応も長引きます。事実として、名称の重複と表記ゆれは、集計の二重カウントや欠品誤認を招きます。
これが重要なのは、1%の取り違えでも月1万件の出荷なら100件の返品・再送が発生し、送料や人件費がそのまま利益を削るからです。加えて、検索や分析の精度が落ちると、売れ筋の判断を誤り、在庫が過不足になります。担当者は次の3点を徹底すると、混乱を素早く減らせます。
- 許可する語彙の一覧と命名ルールを決め、全員が共有する
- 禁止表記(例:色の略語混在)を辞書で機械チェックする
- 例外は理由と期限を明記し、必ず見直し日を入れる
SKU変更時の移行ミス
SKUを改番するときに起きやすいのが「移行ミス」です。商品マスタだけを更新して、受注データ、棚ラベル、ECの商品ページ、広告リンクなどを更新し忘れるケースが典型的です。よくあるのは、旧SKUで注文が入り、システム上は在庫0と表示されて欠品に見えるのに、実際の倉庫には新SKUで在庫が残っているという状況です。この結果、販売機会を逃すだけでなく、現場が突発的な手作業で在庫を調整せざるを得なくなります。
こうしたミスが厄介なのは、「売上の取りこぼし」「二重在庫の発生」「現場の残業」といった負の要素が同時に起きてしまうことです。そのため、SKU改番の際は順序と期間を決めて、計画的に移行することが欠かせません。
安全に移行するには、まず旧SKUと新SKUの対応表(マッピング)を作成し、対象を一覧化します。そのうえで在庫を一括で付け替え、旧SKUでの新規受注を止めます。さらに、旧SKUを使った検索や外部リンクが新SKUへ自動転送されるように設定しておけば、販売の機会を逃しません。一定期間は旧SKUを「別名(エイリアス)」として残し、検索やシステム内で参照できるようにしておくと安心です。最後に、WMS(倉庫管理システム)とECサイトの両方でテスト注文を行い、棚ラベルやバーコードを同じタイミングで差し替えることで、現場とのズレを防げます。
廃番・統合SKUの扱い
シーズン終了やモデル統合で商品が廃番になったとき、そのSKUを放置してしまうとトラブルのもとになります。注文が入ってから「実はもう販売していません」と連絡すれば、お客様の信頼を大きく損ねてしまいます。さらに、古い商品ページやコードを消すだけでは、検索やリンクで訪れたお客様が行き場を失い、販売のチャンスを逃してしまいます。
重要なのは、廃番対応が 在庫管理だけでなく、顧客体験や検索流入(SEO)に直結する という点です。そこで、処理は段階的に進めるのが基本です。
まず、社内では旧SKUを「販売停止」に設定し、在庫を残さず消化します。そのうえで、ECサイトでは旧ページに「販売終了」と明記し、後継商品がある場合はそのページへリンクを貼ります。完全に代替品がない場合も、ページをただ消すのではなく、404(エラー)ではなく410(完全削除を示すコード)を返すことで、検索エンジンに正しく伝えることができます。
また、統合SKUに切り替える際は、色やサイズなどの商品属性を正しく引き継ぐことが大切です。加えて、価格比較サイトや広告リンクも更新しておかないと、売れない旧商品ページにクリックが集まり、無駄な広告費が発生してしまいます。
要するに、廃番SKUは「販売停止 → 在庫消化 → 代替案内」という順序で段階的に処理し、在庫・顧客・検索のすべてに配慮することが、ムダなコストと機会損失を防ぐ一番の方法です。
SKU:よくある質問
まとめ|SKUを正しく理解して在庫と販売を強くする
SKUは、一見ただの管理番号のように思えるかもしれません。しかし、実際には在庫を正しく数え、売上を最大化するための「共通の言語」です。色やサイズ、容量ごとに商品を区切ることで、現場とバックオフィス、店舗とEC、倉庫と仕入先が同じ基準で会話できるようになります。この仕組みが整うと、棚卸やピッキングの精度が高まり、販売データをSKU単位で分析することで仕入れや販促の判断もより的確になります。つまりSKUは、単なるコードではなく在庫管理・販売戦略・顧客体験を結びつける基盤といえるのです。

在庫管理やSKU運用を含め、物流は企業活動の根幹を支える重要な仕組みです。しかし、多品種少量化やEC拡大などにより、現場のオペレーションやシステムにはこれまで以上に柔軟性と正確性が求められています。
SBSリコーロジスティクスは、磨き上げた現場力と業務設計力に加え、最新の物流DXやロボティクスの導入力、そして国内外に広がる物流ネットワークを強みとしています。これにより、在庫の精度向上からコスト最適化、さらには事業成長に寄与するロジスティクス戦略までを一貫してサポートすることが可能です。
変化の激しい市場環境のなかで、物流を安心して任せられる体制を整えることは、企業の競争力を支える大きな力となります。SBSリコーロジスティクスは、在庫管理から物流戦略までお客様と力を合わせて課題を乗り越え、お客様のビジネスの成長を後押しします。
SBSリコーロジスティクスの物流サービス
SBSリコーロジスティクスでは、BtoB配送に特化した高品質な物流サービスを提供しています。精密機器から通販物流まで、信頼と柔軟性を兼ね備えたトータル物流ソリューションをお探しの方は、ぜひこちらから詳細をご覧ください。
- 3PLとは? 意味や導入メリット、事業者選びのポイントなど解説
- サプライチェーンとは? 意味や具体例を交えて徹底解説
- ロジスティクスとは? 物流との違いや課題・今後など徹底解説
- 物流とは? 機能や効率化メリット、ロジスティクスとの違いなど解説
- 物流センターとは? 役割や種類、メリット・最適化についてなど解説
- 物流倉庫とは? 役割や種類、メリット・最適化についてなど解説
- 保管とは? 物流における保管について徹底解説
- キッティングとは? 作業内容やサービス選定のポイントなど徹底解説
- WMSとは? サプライチェーンを変革する、倉庫管理システムの力
- WESとは? 倉庫運営の効率化と自動化を実現するシステムを解説
- WCSとは? 倉庫運営を変革するWCSの全貌
- ラストワンマイルとは? 顧客接点となる、物流のラストワンマイルの重要性とその未来
- 2024年問題とは? 基礎知識、その影響や対応策、そして今後の展望など解説
- 運送会社とは? 役割と種類・分類、DX事情、選ぶポイントなどを解説
- リードタイムとは?意味・計算方法・短縮事例を徹底解説
- 送り状とは? 種類・作成方法・電子化まで徹底解説
- 棚卸とは? 物流現場での意味・手順・課題・改善策を徹底解説
- ロットとは? 物流における基本意味・使われ方・管理の重要性をやさしく解説
- SKUとは何か? 意味・目的・設計・管理・ツール・最新動向まで徹底解説
- ピッキングとは? 意味・種類・効率化の工夫をわかりやすく解説